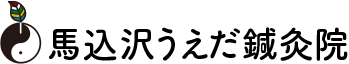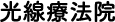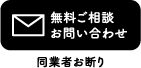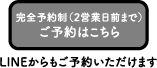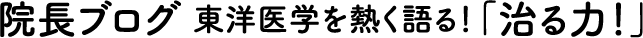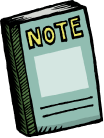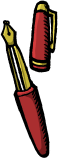ストレス性(視床下部性)不妊
2023/12/31
― なぜストレスによって不妊が起こるのか ―
前章でお話ししたように、女性ホルモンの分泌は「視床下部 → 下垂体 → 卵巣」という脳と卵巣の連携によってコントロールされています。
このうち最も上位にあり、全体のバランスを司っているのが**視床下部(ししょうかぶ)**です。
視床下部は、体温・睡眠・食欲・自律神経の働きなどを整える“体の司令塔”でもあります。
そのため、心身に強いストレスがかかると、真っ先に影響を受けやすい場所でもあるのです。

⚓ ストレスがホルモンのリズムを乱すしくみ
精神的なストレス(人間関係・仕事・プレッシャーなど)や、肉体的なストレス(過労・睡眠不足・過度な運動・急なダイエットなど)が続くと、視床下部の働きが鈍くなります。
すると、本来は視床下部が一定のリズムで出すはずの
**GnRH(卵胞刺激ホルモン放出ホルモン)**の分泌が不安定になります。
その結果、下垂体から分泌される
**FSH(卵胞刺激ホルモン)やLH(黄体形成ホルモン)**の分泌も乱れ、
卵巣に正しい指令が届かなくなってしまいます。
つまり、「脳が卵巣にうまく指示を出せない」状態になるのです。
そのため卵胞が十分に育たず、排卵が起こらない、月経が止まるといった症状が現れます。
これが、いわゆる視床下部性無月経(ししょうかぶせいむげつけい)やストレス性不妊です。
⚖️「心の負担」が「体の不調」として現れる
視床下部は「心」と「体」の境界にあるような存在で、精神的な不安や緊張をすぐに身体の反応として表します。
たとえば、強いストレスを感じると
月経が遅れる
排卵が止まる
基礎体温が安定しない
といった変化が起きるのは、まさにこのためです。
特に、真面目で頑張りすぎる人や、常に人のために動いてしまう人ほど、知らず知らずのうちにこの“脳の疲労”を溜めてしまいます。
🌿東洋医学から見るストレスと不妊
東洋医学では、このような状態を「気の滞り(気滞)」や「肝(かん)の失調」として捉えます。
「肝」は気血の流れや情緒の安定を司る臓とされ、ストレスによって肝の働きが乱れると、全身の気の流れが滞り、血のめぐり(血流)にも影響が及びます。
その結果、子宮や卵巣への血流も悪くなり、卵の育ちや着床の環境にも影響が出ると考えられています。
つまり、東洋医学的にも「ストレスが不妊の原因になる」という考えは、現代医学の視床下部性不妊と非常に通じるものがあるのです。
💡まとめ
ストレス性(視床下部性)不妊とは、心の緊張や疲労が脳の働きを乱し、ホルモンのバランスを崩してしまうことで起こる不妊の一種です。
「心と体はつながっている」ということを、科学的にも東洋医学的にも示す典型的な例といえます。
妊娠しやすい体づくりのためには、単にホルモンを整えるだけでなく、
心をゆるめ、安心できる時間を持つことがとても大切です。

🌞不妊症や生理痛など、女性特有の症状には体をやさしく整える「光線療法」もおすすめしています。
体を内側から温め、ホルモンバランスを整えるサポートを行っています。
👉 光線療法による婦人科系ケアはこちら