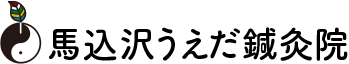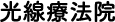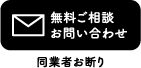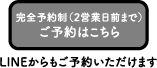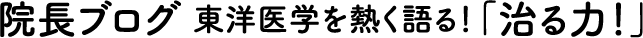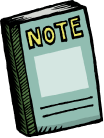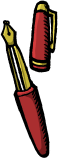子宮内膜症
2023/12/31
子宮内膜症とは、本来子宮の内側にしか存在しないはずの「子宮内膜(しきゅうないまく)」という組織が、子宮の外側(卵巣や腹膜など)にできてしまう病気です。
この「迷い出た内膜組織」も月経周期に合わせて反応し、月経時に出血を起こすため、**強い痛みや炎症、癒着(ゆちゃく)**を引き起こします。

現代医学では、主な症状として以下が挙げられます。
・強い月経痛(回を重ねるごとに悪化することが多い)
・排便時や性交時の痛み
・不妊(卵管や卵巣の癒着による)
・慢性的な下腹部の重だるさ
原因はまだ完全には解明されていませんが、「月経血の逆流説」や「免疫異常説」などが有力です。
🌿 東洋医学からみた子宮内膜症
東洋医学では、子宮内膜症を**「気血の流れが滞り、瘀血(おけつ)が長く停滞した状態」**と捉えます。
「瘀血(おけつ)」とは、血の流れが悪くなり、体内に古い血が滞った状態を指します。
これが子宮周辺に生じることで、痛みやしこり、不妊といった症状が現れると考えます。
以下のようなタイプに分けて、体質や原因を見極めます。
① 気滞血瘀(きたいけつお)タイプ
ストレスや感情の抑圧が原因で「気」が滞り、それに伴って「血」も流れにくくなる状態。
特徴: 下腹部の刺すような痛み、経血に血塊、月経前から痛みが強まる、胸や脇の張り。
→ 「気」と「血」の巡りを促すことで、痛みや詰まりを緩和します。
② 寒凝血瘀(かんぎょうけつお)タイプ
体の「冷え」によって血流が悪くなり、瘀血を生じた状態。
特徴: 冷えると痛みが強くなる、温めると楽になる、経血が黒っぽく粘り気がある。
→ 体を内側から温めて血の流れを改善し、痛みを軽減します。
③ 気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ
慢性的な月経過多や出血、疲労などで「気」や「血」が不足した状態。
特徴: 鈍い痛み、倦怠感、顔色が悪い、めまい、冷え性。
→ 「補気」「補血」を中心に体の基礎力を整え、再発を防ぎます。
④ 湿熱瘀阻(しつねつおそ)タイプ
体内に余分な湿気や熱がこもり、血の流れを妨げている状態。
特徴: 下腹部の熱感、経血の色が濃く粘る、口の渇き、便秘ぎみ。
→ 「湿」と「熱」を取り除き、体内環境を清潔に整えることで改善を図ります。
☯ 鍼灸や漢方のアプローチ
鍼灸では、「気血の滞り」を解き、子宮や卵巣周辺の血流を促進することで、炎症・痛み・冷えの改善を目指します。
また、体全体のバランスを整えることで、ホルモン分泌や自律神経にも良い影響を与え、不妊や月経不順の改善にもつながることがあります。
漢方薬では、「血の滞り」を取る**活血化瘀(かっけつかお)**を中心に、体質に合わせた処方(桂枝茯苓丸・桃核承気湯・温経湯など)が選ばれます。
💡 まとめ
東洋医学では、子宮内膜症を「単なる病変」ではなく、心身のバランスの乱れが現れた状態として捉えます。
そのため、治療は「子宮だけ」でなく、「全身の巡りと調和」を回復することを目的としています。
治療方法は主に薬物療法となります。薬の効果をあまり感じられず、手術に至る人もいますが、手術後に再発するケースも少なくありません。
また、子宮内膜症は不妊の一因となることもあるため、早期からの適切な治療と体質改善の両立が大切です。

🌞不妊症や生理痛など、女性特有の症状に体をやさしく整える「光線療法」もおすすめしています。体を内側から温め、ホルモンバランスを整えるサポートを行っています。
👉 光線療法による婦人科ケアはこちら