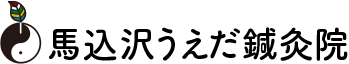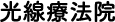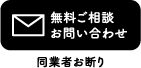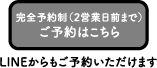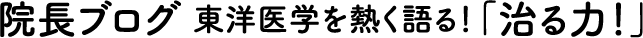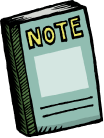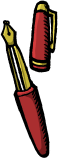月経痛
2023/12/31
月経痛(げっけいつう)は、月経(生理)の前後や期間中に下腹部や腰に痛みを感じる症状のことです。痛みの程度には個人差があり、軽い鈍痛程度で済む方もいれば、鎮痛薬を手放せないほど強い痛みに悩まされる方もいます。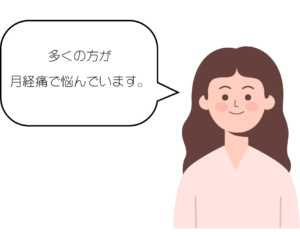
現代医学的には、子宮内膜から分泌される「プロスタグランジン」という物質が子宮を強く収縮させ、血流を一時的に悪くすることで痛みが生じるとされています。また、子宮内膜症や子宮筋腫などの疾患によって起こる場合もあります。
一方、**東洋医学では月経痛を「気血の流れが滞った状態」**と考えます。
「気(き)」とは、体を動かすエネルギーであり、「血(けつ)」は全身を巡る栄養物質です。
この二つがスムーズに巡っていれば、月経も順調に行われますが、どちらかが滞ると痛みや不調が現れやすくなります。
とくに東洋医学では、月経痛の主な原因を以下のように捉えます。
① 気滞(きたい)
ストレスや感情の抑圧により「気」の流れが滞るタイプ。
特徴:張るような痛み、胸や脇のつかえ、ため息が多い。
→「気」の巡りを良くすることで痛みが和らぎます。
② 血瘀(けつお)
「血」の流れが悪く、子宮の中に滞りがあるタイプ。
特徴:刺すような痛み、経血に血の塊、色が黒っぽい。
→血の巡りを整え、滞りを取り除くことが大切です。
③ 寒凝(かんぎょう)
体の「冷え」が原因で気血の流れが悪くなったタイプ。
特徴:冷えると痛みが強くなる、温めると楽になる。
→体を温めることで子宮の働きを取り戻します。
④ 気血両虚(きけつりょうきょ)
慢性的な疲労や過労、食事の偏りなどで気血が不足したタイプ。
特徴:痛みは軽めだが長引く、倦怠感や顔色の悪さを伴う。
→「補う」ことで体のバランスを整えます。
このように、東洋医学では痛みそのものだけでなく、体全体の状態(体質)や生活の背景を見ていくのが特徴です。
そのため、同じ「月経痛」でも人によって治療方針は異なります。
鍼灸では、ツボを使って「気血の流れ」を整え、体を内側から温めることで子宮の働きを改善していきます。結果として、月経痛の軽減だけでなく、ホルモンバランスの安定や冷え・不妊の改善にもつながることがあります。
症例:月経痛も軽減、妊娠することができた
症例:月経痛が軽くなり、妊娠に至る
🌞不妊症や生理痛など、女性特有の症状に体をやさしく整える「光線療法」もおすすめしています。体を内側から温め、ホルモンバランスを整えるサポートを行っています。