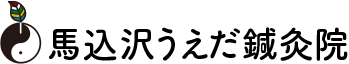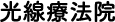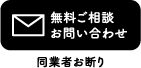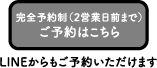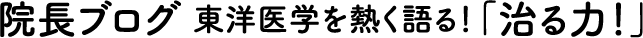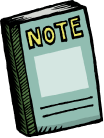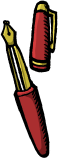不眠症と肩凝り
2019/10/18

上田
鍼灸でみんなを幸せにしたいと
日々精進

roo
出身地:千葉
好きな食べ物:肉

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo

上田

roo
姿勢を維持するための筋肉が働かなかったり、
逆にただ立っていればいいだけなのに、
異常に力が入ってしまっては困ります。
そんなの疲れてしょうがない。
普通は中枢(脳脊髄)と筋肉との間で常に情報のやり取りが
行われていますから、そんなことにはなりません。
筋肉の状態を良好に保つための神経がAγニューロン。
脳幹毛様体というところから筋肉に向かって
伸びています。
Aγニューロンという頼もしい味方がいるのにも関わらず、
肩凝りは起こります。
過度に筋肉が緊張する状態が続くと
脳幹毛様体からのAγニューロン系に異常が生じ、
筋肉を理想の状態に保つことができなくなって、
結果、肩凝り、というわけ。
肩こりを緩和させるには、凝っている筋肉を伸ばしたり、
ギュッと掴んだりするのが効果的です。
がしかし、それだけで肩凝りが解消された状態が
長く続かないのは、多くの人が経験済み。
ストレスが肩凝りを悪化させますから、
肩凝り解消のためには、
暗い所で、目を閉じて、横なるのがgood。
リラックスのための音楽を流したり、
好みの香りを嗅ぐのもいいでしょう。
しっかりと睡眠を取ってエネルギーを蓄えねばなりませんが、
肩凝りが邪魔をして眠れない。
そんなときは肩凝りと不眠の両方に働きかける治療が効果的です。
「脳幹毛様体、Aγニューロンを賦活させて、大脳皮質を休める」
これはつまり、東洋医学でいうところの
気や血を司る肝を良好な状態にして上亢した肝火を下ろす
ことに他なりません。

肩こり
不眠の悩み
マッサージが肩コリに効く理由1
マッサージが肩コリに効く理由2
マッサージが肩コリに効く理由3
マッサージが肩こりに効く理由4
薬・気晴らし・そして
きいちろぶろぐ・睡眠
きいちろぶろぐ・不眠症
不眠の悩み
薬・気晴らし・そして
今陰陽論3
今陰陽論
名人でも
寝て、待つ秋
頼りになるもの
PM9
ゆっくり行こう
超人こそ
眠い人
力みと緩み
休み明け2
休み明け
眠りの邪魔をしない
眠らなかったからといって
夜型、朝方
就寝と起床
ボーッ
睡眠孝行
オキシトシン
とてもとても大きな音のする場所で眠れるか?
失眠
コンディショニングを成功させる
護身
良きにつけ悪しきにつけ
相関性
認知症のツボ
徹夜
早馬
人間は眠くなっても
眠る
変な時間に起こされて
眠る時間
発熱毛布
ただ寝る
「寝ないと太る」は本当か?
適度に適切に
なんで鍼を打つのか?
公慶上人は楽しかったんだ
起床時間
畳一畳の軽井沢
Serious
若い女性と睡眠障害
寝汚い人
陰虚
不眠の悩み
朝ごはん
陰と陽
いつもより早く眠くなる
定着のための時間
夕顔丸の船室で
パジャマ
ふとん
いろはがるた「ね」
なんで鍼を打つのか?