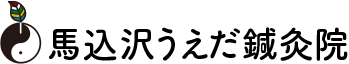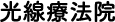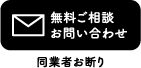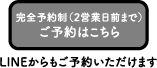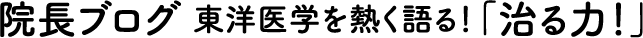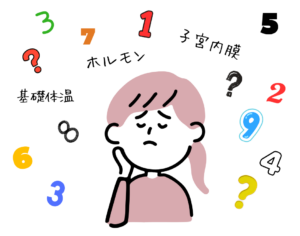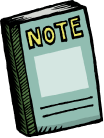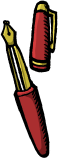睡眠と妊娠
2025/11/29
■ 数字で見る「眠り」の重要性
妊活に限らず、健康な体づくりにおいて睡眠が重要であることは、もはや説明するまでもありません。
体を回復させ、ホルモンを整え、日中の活動の質を高める。
睡眠は、私たちのポテンシャルを引き出すための“土台”です。
それは妊娠においても同様です。
今回はあえて、「感覚」ではなく「数字」に目を向け、
睡眠と妊娠の関係が、統計的にどのように示されているのかを整理してみたいと思います。
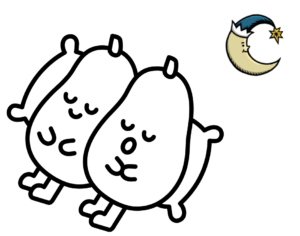
■ 妊娠率は「妊娠までにかかる時間」で評価される
睡眠と妊娠の研究でよく用いられる指標に、
**TTP(Time To Pregnancy:妊娠に至るまでの期間)**があります。
これは、
-
結婚してからの年数
-
妊活を始めてからの月数
といった曖昧なものではなく、
「避妊をせずに妊娠を試み始めてから、実際に妊娠が成立するまでの期間」
を指します。
このTTPが短いほど「妊孕性が高い」、
長いほど「妊孕性が低い」と評価されます。
研究では、女性・男性の年齢、BMI、喫煙歴などの影響を統計的に調整したうえで、
睡眠時間とTTPの関係が解析されています。
■ 睡眠時間と妊孕性の関係(統計的傾向)
複数の疫学研究を総合すると、
睡眠時間と妊娠のしやすさには、次のような傾向が見られます。
-
睡眠時間が短い(おおむね6時間未満)
-
1周期あたりの妊娠確率が低下
-
妊娠に至るまでの期間が延びやすい
-
-
睡眠時間が適切(7〜8時間前後)
-
妊孕性が最も高い群
-
妊娠に至るまでの期間が短い傾向
-
-
睡眠時間が長すぎる(9時間以上)
-
妊孕性が再び低下する傾向
-
つまり、睡眠時間と妊娠率の関係は、
「短すぎても、長すぎても下がる」U字型を描きます。
■ 「長く寝ると妊娠しにくい」の本当の意味
ここで誤解してはいけないのは、
「長く寝たこと自体が、妊娠に悪影響を与えた」
という意味ではない、という点です。
9時間以上の睡眠が必要な人は、
-
慢性的な疲労
-
回復力の低下
-
自律神経やホルモン調整力の低下
-
睡眠の質の低下
といった背景を抱えていることが少なくありません。
つまり、
「長時間睡眠」は原因というより、“体の状態を映す指標”
と考える方が自然です。
■ なぜ睡眠が妊娠に影響するのか
睡眠は、妊娠に関わる多くの仕組みに影響します。
-
視床下部―下垂体―卵巣系(HPO軸)
-
排卵リズム
-
黄体機能
-
メラトニン分泌
-
ストレスホルモン(コルチゾール)
これらは年齢とは別の次元で、
**「今の体の状態」**を反映する要素です。
そのため、年齢を統計的に揃えて比較した場合でも、
十分な睡眠が取れている人の方が、妊娠に至るまでの期間が短い
という結果が示されます。
■ 数字は「評価」ではなく「目安」
もちろん、
-
短時間睡眠でも妊娠する人はいます
-
よく寝ていても妊娠に時間がかかる人もいます
数字は未来を決めるものではありません。
しかし、
数字は「現実を知るための目安」にはなります。
睡眠時間は、
-
体が回復できているか
-
今の生活が無理なく回っているか
-
ポテンシャルを十分に発揮できているか
を映す、一つの分かりやすい指標です。
■ まとめ:睡眠は「妊娠のため」だけではない
睡眠は、
妊娠のためだけに大切なのではありません。
-
日中を快適に過ごすため
-
体を健康に保つため
-
本来持っている力を引き出すため
その延長線上に、妊娠があります。
数字はあくまで目安。
けれど、その数字が示す「体からのサイン」には、
一度、耳を傾けてみる価値があります。
睡眠を整えることは、
妊活のためであると同時に、
自分の体を大切に扱うことそのものなのです。
不妊症に悩む船橋市のあなたへ